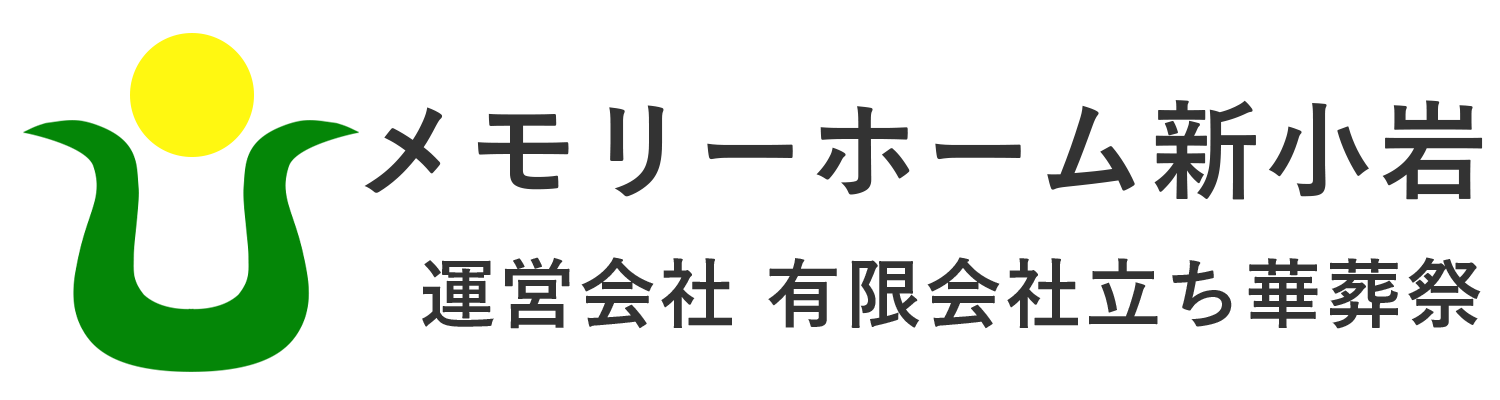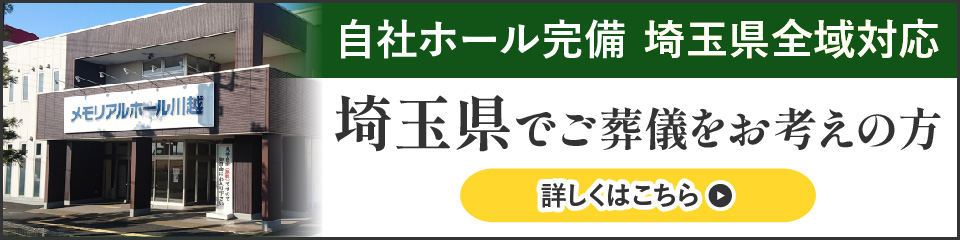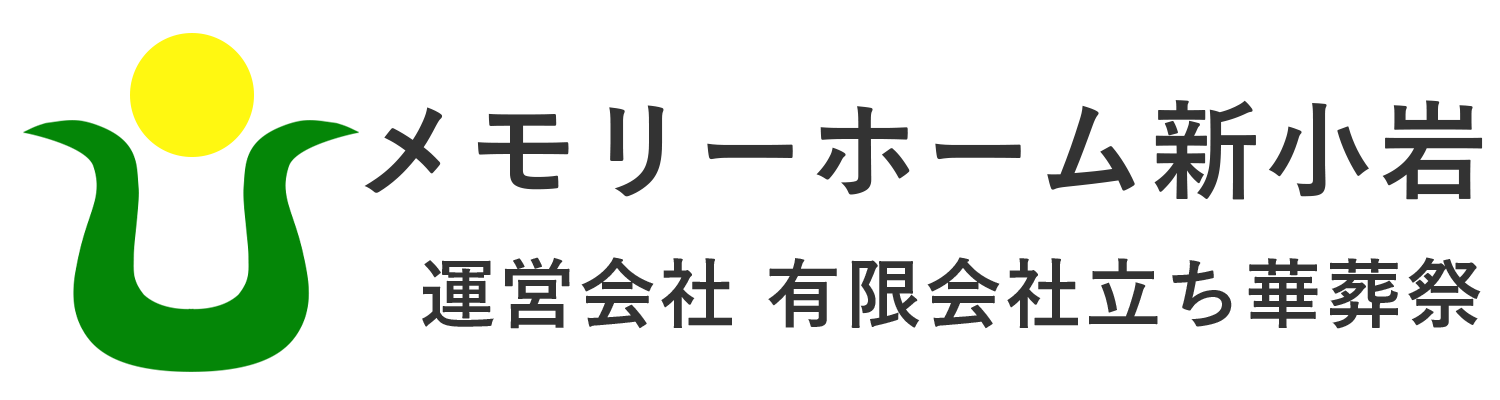親族や身近な方が亡くなり、葬儀費用の負担に不安があるときに知っておくべきのが「葬祭扶助」です。本記事では、葛飾区で葬祭扶助を使って実質0円で直葬(火葬式)を行うための具体的な手順を、窓口対応から葬儀社への伝え方、夜間対応、却下時の対処まで、誰が何をいつすべきかをチェックリスト形式で整理しています。短時間で確実に動ける実務ガイドです。

この記事を書いた人
立ち華葬祭 COO 高橋 哲彦
葬儀業界歴20年。その中で対応した葬儀の施行件数は3000件以上。
現在は葬儀社「立ち華葬祭」でCOO(最高執行責任者)として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。そしてその専門知識や経験をもとに、葛飾区を中心とした方々に葬儀の役立つ情報をご提供しています。
生活保護葬(葬祭扶助)とは何か
葬祭扶助は生活保護法に基づく葬儀費用の公的扶助で、経済的に困窮する被保護者やその遺族が対象になります。支給は「必要かつ相当な範囲」が基準で、遺体の搬送や安置、棺、火葬料など最低限の費用が対象です。制度の趣旨は「速やかに尊厳を保った埋葬を行う」ことであり、過度な祭壇や通夜・告別式の豪華化は対象外となります。
申請は原則として葬儀前に行い、自治体の認定が下りれば自治体と葬儀社で直接精算する仕組みが一般的です。夜間や緊急時でもまずは最低限の搬送・安置を行い、領収書を保管して翌営業日に窓口で申請する流れを押さえておくことが重要です。
対象者と受給要件(誰が使えるか)
主な対象は、死亡した時点で生活保護を受けていた本人、もしくは遺族が生活保護を受けていて葬儀費用を負担できない場合です。遺族が不在で自治体が埋葬する行政埋葬に相当すると判断されるケースでも実施されます。制度適用の判断には故意や第三者責任、相続財産や保険の有無などが考慮されるため、事前に窓口で状況説明を行うことが不可欠です。
具体的には、故人または遺族に支払能力がないことが前提で、相続財産や保険金がある場合は支給が見直される可能性があります。申請前に担当窓口に状況を説明し、必要書類や証明の準備方法を確認しておくと手続きがスムーズになります。
葬祭扶助でカバーされる費目と目安
葬祭扶助がカバーするのは原則として火葬までの基本項目です。一般的に検案・搬送・安置・棺・簡易納棺・ドライアイス等の保全・火葬料・骨壺などが含まれ、自治体の基準(級地や年齢など)に応じて支給されます。多くの自治体では成人で数十万円前後を目安に上限を設けていますが、具体的な金額や扱いは自治体ごとに異なります。
したがって、葛飾区の基準を窓口で確認することが重要です。対象外となる可能性が高い項目(通夜・告別式の費用、宗教謝礼、祭壇のグレードアップなど)は自己負担と想定し、見積りで扶助対象と自費部分を明確に分けてもらっておくと後のトラブルを防げます。
葛飾区の申請窓口と手続きフロー(死亡発生〜決定まで)
まず死亡を確認したら、救急や警察が関与する必要があるかを優先的に判断します。その後、遺体搬送や安置は夜間であっても葬儀社に依頼し、必ず領収書を受け取って保管してください。一般的な流れは①遺体搬送と安置(夜間は葬儀社へ)→②福祉窓口へ葬祭扶助の事前相談・申請→③申請書類の提出と審査→④扶助決定後に自治体と葬儀社で精算、となります。
申請書類や必要な証明書類(死亡診断書、身分関係資料、見積書、領収書など)は窓口で確認のうえ、可能な限り翌営業日に持参してください。夜間対応で一時的に進めた措置は、支給決定前に実行すると支給不可となるリスクがあるため、最低限に留める指示を守ることが求められます。
夜間・緊急時の対応と指定葬儀社の選び方
夜間や休日に亡くなった場合、区役所の担当者は常駐していないことが多いため、まずは遺体保全のために葬儀社に連絡し搬送・安置を依頼します。ここで重要なのは必ず領収書を受け取ることと、葬儀社が葬祭扶助対応の実績があるかを確認することです。領収書は後日の申請や精算で必須書類になります。
葬儀社を選ぶ際のチェックポイントは「葬祭扶助対応の実績」「自治体への請求経験」「見積りで扶助対象と自費を明確に分けているか」「24時間対応かどうか」です。支払方法(自治体の直接支払か、一時立替の後精算か)も事前に確認し、可能であれば書面で取り決めておくと後のトラブルを避けられます。
自己負担になりやすい項目とトラブル回避の実務
扶助対象外になりやすい項目には、祭壇のグレードアップ、通夜・告別式の実施、香典返し、宗教者への慣習的謝礼、長期安置による追加費用などがあります。これらは制度上「必要かつ相当な範囲」を超えるため自己負担になるのが一般的です。事前に費用負担の範囲を確認しないと想定外の請求が発生します。
トラブル回避の実務としては、葬儀社に対して「葬祭扶助前提」であることを明示し、扶助対象と自費項目を分けた見積書を必ず取得・保存してください。見積りはPDFや写真で保存し、窓口で一項目ずつ確認を取ることで認識のズレを防げます。また、支給決定前に過度な実施を避け、夜間は最低限の措置に止める判断を優先してください。
支給却下・減額時の対応と不服申し立ての進め方
支給却下や減額の通知を受けた場合、まず却下理由を文書で求め、申請書・見積書・死亡診断書・領収書など関連資料を整理します。窓口で再審査を申し入れる際には、理由書と証拠書類を提示して冷静に説明することが重要です。担当者名と日時は必ず記録してください。
それでも解決しない場合は、審査請求や行政相談、社会福祉協議会、法テラスなどの支援機関に相談する手順が一般的です。これらの機関は申立てのサポートや法的助言を提供してくれるため、早めに利用することで解決の可能性が高まります。
よくある質問
葬祭扶助の申請はいつまでに?
原則として葬儀前に申請します。夜間に訃報が発生した場合は、まず葬儀社に搬送を依頼して領収書を取得し、翌営業日に葛飾区の福祉窓口で事前相談と申請を行ってください。窓口での確認により扶助対象の範囲がはっきりするため、事前申請が原則であることを念頭に置いてください。
夜間対応で一時的に行った措置は、支給決定前に過度に進めると支給不可になるリスクがあります。最低限の安置措置と領収書の確保を優先し、窓口での指示に従ってください。
夜間に葬儀社を呼んでも大丈夫か
大丈夫です。ただし搬送は最低限に留めて葬祭扶助の対象に準拠した対応を依頼し、必ず領収書を受け取ってください。夜間は役所が対応できないため葬儀社の協力が不可欠ですが、後日窓口で扶助対象の確認を受けるまでは不要な費用を発生させないように注意が必要です。
葬儀社を選ぶ際は扶助対応実績があるかを確認し、見積りで扶助対象と自費を明確に分けるよう求めてください。支払方法(自治体直接払いか立替か)も事前に確認し、書面で合意を取ると安心です。
却下された場合の次の手順は
却下理由を文書で受け取り、申請書類や領収書、見積書などの関連資料を整理して再審査を申し出ます。窓口での説明が十分でなければ、担当者名や日時を控えておくと後の手続きで役立ちます。再審査で解決しない場合は審査請求や行政相談、社会福祉協議会や法テラスなどの支援を活用してください。
これらの支援機関は申立ての方法や法的助言を提供してくれるため、早めに相談することで解決の糸口が見つかることが多いです。感情的にならず、証拠資料を揃えて冷静に手続きを進めることが近道です。
まとめ
葬祭扶助は生活保護受給者や経済的に困窮する遺族が対象で、搬送・安置・棺・火葬料など最低限の費用を自治体が負担します。夜間は葬儀社に搬送を依頼し領収書を取得して翌営業日に葛飾区福祉窓口で申請、見積りは扶助対象と自費を分けて確認し、決定前の過度な実施は避けてください。却下時は理由書を求め、再審査や支援機関に相談することが解決への近道です。