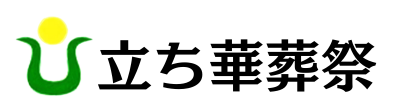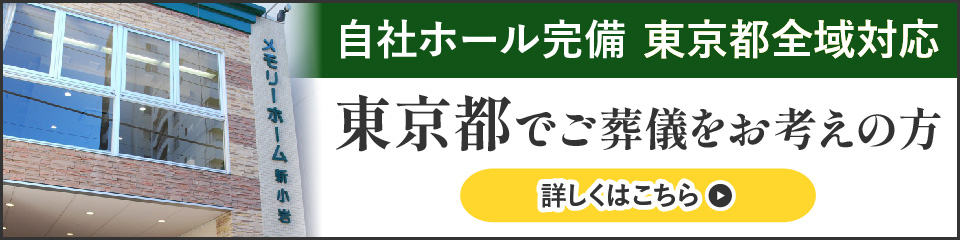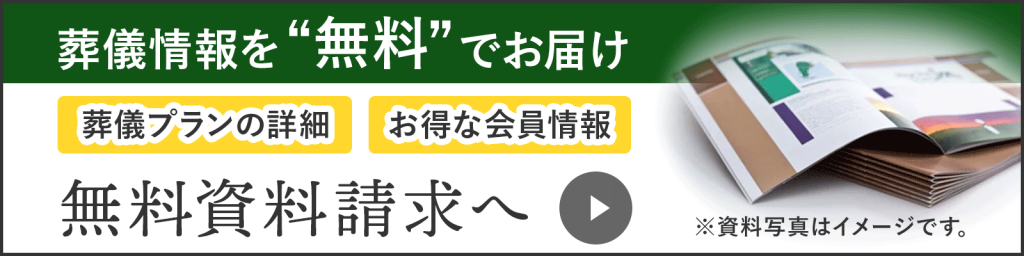急な訃報で「追悼式か告別式か」を即決しなければならない場面は少なくありません。本記事は、両者の目的と雰囲気の違いを明確に整理し、川越市での会場選び、役所手続き、香典や服装の実務チェックリスト、式次第の例、弔辞テンプレ、宗教別の注意点、社葬対応までを実用的にまとめました。担当者が速やかに動けるよう、当日の持ち物リストや案内文のポイントも併記しています。

この記事を書いた人
立ち華葬祭 COO 高橋 哲彦
葬儀業界歴20年。その中で対応した葬儀の施行件数は3000件以上。
現在は川越市の葬儀社「立ち華葬祭」でCOO(最高執行責任者)として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。そしてその専門知識や経験をもとに、川越市を中心とした方々に葬儀の役立つ情報をご提供しています。
追悼式と告別式、何が主目的でどう雰囲気が違う?
告別式は宗教的儀礼を中心に「正式な別れ」を行う場で、読経や焼香が主体になります。形式や所作が重視され、親族や近親者が中心となって執り行うことが一般的です。式の流れや時間配分も宗旨や寺院の慣例に合わせて決める必要があります。
一方、追悼式(追悼会・お別れ会)は後日に開かれることが多く、映像やスピーチで思い出を共有する社交的な集いです。宗教色を薄め、友人や職場の関係者など幅広い参列者が集まりやすい雰囲気が特徴です。目的を明確にすることで、参列者の期待に応えられます。
どの軸で選べばよい?判断チャート
選択は主に「宗教性」「参列者の範囲」「時間と費用」の三軸で考えると分かりやすいです。故人の遺志や遺族の希望を最優先に、宗教儀礼を重視するなら告別式、広く関係者へ思い出を共有したいなら追悼式を選びます。判断基準を明文化しておくと関係者間でのズレを防げます。
急ぎで両方が必要な場合は、簡易の告別式を葬儀当日に行い、後日追悼式を開く二段構えが実務的です。費用や日程調整の都合も踏まえ、葬儀社と早めに相談してプランを立ててください。
川越市での初動と実務チェックリスト
川越市ではまず医師の死亡診断書を受け取り、死亡届を市役所に提出します。並行して葬儀社へ連絡し、搬送と安置場所の確保、斎場の仮押さえを行うのが基本的な初動です。公営斎場は火葬場併設のところも多く、搬送や費用面で利点があります。
以下は初動で優先する項目と注意点の一覧です。担当者はこの流れを同時並行で進めることが重要で、書類や連絡先をすぐ出せるようにしておくと手続きが円滑になります。死亡診断書・葬儀社連絡・役所確認は特に優先してください。
| 手続き | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 死亡届提出 | 医師の死亡診断書を添付して市役所へ | 原則7日以内 |
| 斎場仮押さえ | 参列人数と宗旨を伝え見積もり取得 | 早めに仮押さえ推奨 |
| 僧侶・司会等手配 | 宗派確認、読経時間・謝礼を打合せ | 日程確定後直ちに |
式次第と所要時間の例(川越市で多い型)
典型的な告別式の流れは「開式→読経→弔辞→焼香・献花→閉式」で、所要時間は30分〜90分程度が目安です。宗派や弔辞の数、参列者の規模によって変動しますので、進行時間は式場と細かく詰めておきましょう。
追悼式は「開会→映像・スピーチ→献花→会食・懇談」などが一般的で、通常1〜2時間を見込んでください。会食や映像の有無で準備物や音響設備の手配が必要になりますので、事前にチェックリストで漏れがないかを確認することが大切です。
| 式の種類 | 主な流れ | 所要時間目安 |
|---|---|---|
| 告別式 | 読経→弔辞→焼香・献花→閉式 | 30〜90分 |
| 追悼式 | 映像→スピーチ→献花→会食 | 60〜120分 |
服装・香典・供花の実務マナー
告別式では黒喪服が原則です。男性は黒のダブルまたはシングル、女性は黒のワンピースや黒礼服が基本とされます。追悼式は略喪服やダークスーツで差し支えない場合が多いですが、案内状で服装を指定すると参列者に親切です。
香典は受付があるかどうかを案内で明記し、受け取りを辞退する場合はその旨を案内に記載してください。供花は式場の受入可否を事前に確認し、一般的には白基調で手配します。小さな手順の差が失礼の有無を分けるため、案内文で細部まで示すことが重要です。
- 当日の持ち物:香典袋(中袋記入済み)、袱紗、ハンカチ、弔辞原稿
- 供花手配:式場に受入確認後、白基調で手配
- 服装の案内:招待状や案内状に明記する
弔辞・挨拶のテンプレ(短・中・長)
弔辞の基本構成は「冒頭の弔意→故人との関係→具体的思い出→結びの祈念」です。時間や場の雰囲気に応じて長さを調整し、短い弔辞は一礼と簡潔な謝辞で済ませ、長い弔辞は略歴や感謝の言葉、今後の支援表明などを含めます。
事前に司会と時間配分を共有し、弔辞の順番や読み上げ時間を決めておくと滞りなく進行します。原稿は読みやすい大きさでプリントし、予備の控えを受付または司会に預けると安心です。
宗教別の注意点(仏式・神式・無宗教)
仏式は焼香の作法や回数が宗派で異なります。宗派ごとの慣例を事前に僧侶と確認し、参列者に分かりやすく案内すると混乱を避けられます。読経時間や献花の有無も調整ポイントです。
神式は玉串奉奠など独自の作法があり、神職との事前打合せが必須です。無宗教の場合は儀礼を簡潔にし、黙祷や献花の形式を案内で示すと参列者が迷わずに済みます。どの場合も会場と宗教者との細部確認が重要です。
川越市での会場選びと手配のコツ
川越市内には公営斎場、民間斎場、寺院斎場など選択肢があります。公営斎場は火葬場併設のケースがあり、搬送や費用面で効率が良いのが利点です。民間斎場は会食や演出の自由度が高く、式の内容に合わせた設備が整っていることが多いです。
見学時には駐車場の有無、バリアフリー対応、映像設備、供花受入可否を必ず確認し、書面で見積りを取得してください。また、役所の手続き窓口の案内や火葬日時の確認も同時に進めるとスムーズです。書面で条件を残すことがトラブル防止になります。
社葬や追悼会を職場で行う際の手順
社葬は社内での調整と外部への案内が必要で、実行委員会を設けて細かな役割分担を決めるのが基本です。訃報連絡、式次第作成、受付や誘導の人員手配、案内状の送付といった作業を分担して進めます。メディア対応がある場合は広報担当を事前に決めてください。
案内文には日時・場所・服装・出欠連絡先・駐車場案内などを明記します。当日の役割(受付、会場誘導、弔辞管理、会食係)を事前に割り当て、リハーサルやマニュアルを用意しておくと当日運営が安定します。
- 社葬の基本フロー:訃報連絡→実行委員会→式場手配→案内発送→当日運営→礼状発送
- 案内文に明記する項目:日時・場所・服装・駐車・出欠連絡先
- 当日の役割:受付、会場誘導、弔辞管理、会食係を事前に割当て
必要であれば、本記事の式次第テンプレや挨拶文のワード形式テンプレート、川越市の役所窓口情報に合わせたチェックリストを個別に作成します。急ぎの現場では「死亡診断書・葬儀社連絡・役所確認」を同時に進めると落ち着いて対応できます。
よくある質問
追悼式と告別式は両方必要?
故人や遺族の意向で決めるのが基本です。宗教儀礼を重視するなら告別式を優先し、広く思い出を共有したい場合は追悼式を後日に行う選択が向きます。両方行う「二段構え」は、宗教的な区切りを当日行い、その後に友人・職場関係者を集めて追悼会を開く方法で、近年でもよく採用されています。
二段構えにする場合、当日の告別式は時間を短めに設定し、追悼式で映像やスピーチ、会食などを充実させると参列者の負担も抑えられます。費用や日程調整、会場手配を早めに進めることが成功の鍵です。
服装はどう区別すればいい?
告別式では黒喪服が原則です。男性は黒のスーツや羽織袴、女性は黒のワンピースや礼服が一般的で、アクセサリー類は控えめにします。追悼式は略喪服やダークスーツで問題ない場合が多いものの、参列者の年齢層や故人の関係性を踏まえた配慮が必要です。
案内状に服装の指定(「黒喪服」「平服で可」「ダークスーツ推奨」など)を明記すると参列者が迷わず準備できます。宗教や地域の慣習により差がありますから、迷ったら遺族側から一言添えるのが親切です。
香典や供花は断れる?
受付がある場合は香典を受け取るのが一般的ですが、遺族が香典を辞退する場合は案内に明記しておくと参列者に伝わります。供花についても式場の受入可否を事前に確認し、受け入れない旨を案内に書いておくと手配ミスを防げます。
供花を受ける場合は白基調が一般的ですが、社葬や団体からの供花では規模や配置を式場と相談して決めます。いずれにしても事前の周知と式場との合意が重要です。
まとめ
告別式は宗教儀礼による正式な別れ、追悼式は思い出を共有する集いで、選択は宗教性・参列者範囲・日程で判断します。二段構えも可能で、川越市では死亡診断書取得と死亡届提出、斎場仮押さえ、僧侶手配を優先してください。服装や香典、供花の可否は案内で明示し、式次第や弔辞テンプレを用意すると当日の混乱を減らせます。社葬は実行委員と広報調整が鍵となります。