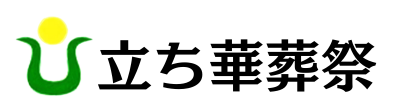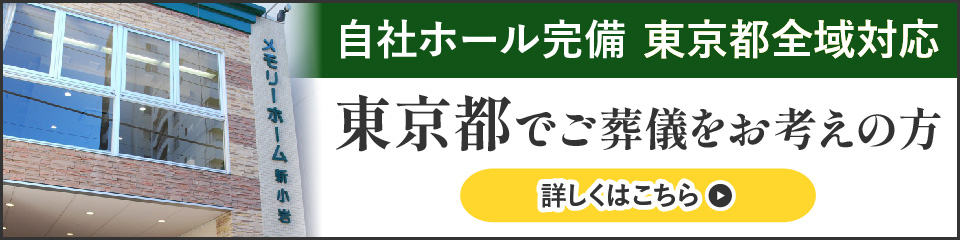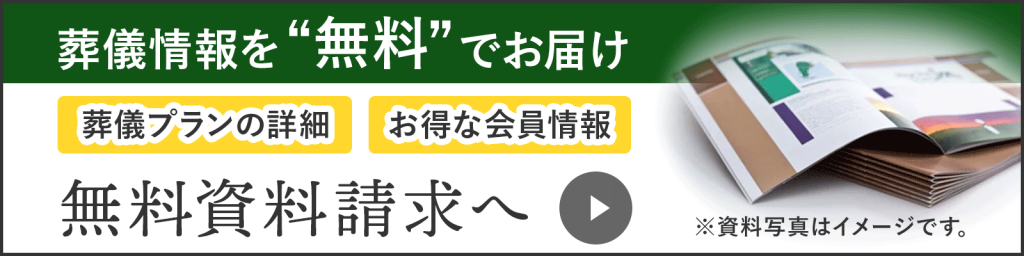大切な方をお見送りした後、その思い出を胸に、ご自宅で故人を偲ぶための祭壇を設けることがあります。
それが「あと飾り祭壇」や「後飾り祭壇」と呼ばれるものです。川越の地でもこの風習は深く根付いており、多くのご家庭で大切にされています。本記事では、あと飾り祭壇の意味や役割、川越における宗派・宗教別の飾り方、そして処分方法について、丁寧にご説明いたします。

この記事を書いた人
立ち華葬祭 COO 高橋 哲彦
葬儀業界歴20年。その中で対応した葬儀の施行件数は3000件以上。
現在は川越市の葬儀社「立ち華葬祭」でCOO(最高執行責任者)として、お客様の理想の葬儀をお手伝いしております。そしてその専門知識や経験をもとに、川越市を中心とした方々に葬儀の役立つ情報をご提供しています。
あと飾り祭壇の意味と役割

あと飾り祭壇は、葬儀や火葬が終わった後にご自宅で故人のご遺骨を一時的に安置するための祭壇です。「中陰祭壇」や「自宅飾り」とも呼ばれ、川越では古くからその大切さが伝えられてきました。
この祭壇を設けることで、故人との最後の時間を大切に過ごすことができます。遺族が心を落ち着かせ、故人を偲ぶ場として機能するだけでなく、弔問客がお参りしやすい環境を整える役割も果たします。
川越の宗派・宗教別のあと飾り祭壇の飾り方

仏教(浄土真宗以外)
仏教では、白木の祭壇を用意し、故人を丁寧にお祀りします。
上段に遺骨や遺影、位牌を置き、中段には香炉や花立て、ろうそく立てなどの仏具を配置します。下段には果物やお菓子などのお供え物を並べます。また、線香やろうそく、生花を飾り、故人への想いを込めます。
- 上段:遺骨、遺影、位牌
- 中段:仏具(香炉、花立て、ろうそく立て)
- 下段:お供え物(果物、お菓子など)
- その他:線香、ろうそく、生花を飾ります
浄土真宗
浄土真宗では、他の仏教宗派と比べてシンプルな飾り方が特徴です。
棚や台に遺骨、遺影、位牌を置くだけで、お供え物や仏具は仏壇に飾ります。中陰壇を設けないことが一般的で、念仏を唱えながら故人を偲びます。
- 遺骨
- 遺影
- 位牌
神道
神道では「仮霊舎(かりみたまや)」と呼ばれる祭壇を用意します。
八足の台に白い布をかけ、遺骨や霊璽(位牌に相当)を安置します。鏡や玉串、神具を飾り、清らかな空間を演出します。川越の神社に相談すると、詳しい作法を教えていただけます。
- 八足(はっそく)の3段の台(2段でも可)
- 白い布(白木の場合は不要)
- 遺骨
- 霊璽(れいじ)※位牌に相当
- 玉串(たまぐし)
- 鏡や剣などの神具
キリスト教
キリスト教では、シンプルなテーブルに白い布をかけ、遺骨や遺影、十字架を置きます。
生花やロウソク、聖書を飾り、パンとワインをお供えします。これらはイエス・キリストの体と血を象徴しています。川越の教会で相談すると、より具体的なアドバイスが得られます。
- 小さいテーブルや台
- 白い布
- 遺骨
- 遺影
- 十字架
- 生花
- パン(イエス・キリストの肉を象徴)
- 聖書
- ロウソク
- お供え物(故人の好きだったものなど)
あと飾り祭壇の設置場所とポイント

あと飾り祭壇は、仏壇がある場合はその前に、ない場合は部屋の北側や西側に設置するのが一般的です。
しかし、川越の住宅事情に合わせて、ご家族が集まりやすく、お参りしやすい場所を選ぶことが大切です。直射日光や湿気の多い場所は避け、清潔で穏やかな空間を心がけましょう。
お供え物について

お供え物は、故人の好物や季節の果物、お菓子などを選ぶと良いでしょう。
ただし、生ものは腐敗の恐れがあるため避け、アルコール類も控えめにします。お供え物は奇数で供えると縁起が良いとされています。川越の銘菓や特産品をお供えすることで、故人との思い出を深めることができます。
あと飾り祭壇の期間と日々のお参り

あと飾り祭壇は、一般的に四十九日の忌明けまで設置します。その間、毎日お参りすることで、故人への想いを伝えることができます。しかし、無理をする必要はありません。忙しい日々の中で、心を込めて手を合わせる時間を持つことが大切です。
あと飾り祭壇の処分方法

忌明け法要が終わった後、あと飾り祭壇の処分を行います。
川越の葬儀社に回収を依頼したり、仏具店に引き取ってもらうことができます。また、紙やダンボール製の祭壇であれば、川越市のゴミ分別ルールに従って処分することも可能です。処分に抵抗がある場合は、専門家に相談し、故人への敬意を持って対応しましょう。
よくある質問

あと飾り祭壇は必ず設置しなければいけませんか?
必ずしも設置しなければならないわけではありませんが、故人を偲び、心の整理をつけるための大切な場となります。川越の伝統やご家族のご意向に合わせて、無理のない範囲でご検討ください。
お供え物は毎日取り替える必要がありますか?
可能であれば毎日新鮮なものに取り替えるのが望ましいですが、難しい場合は数日に一度でも構いません。大切なのは故人への想いを持ち続けることです。
あと飾り祭壇の処分はいつ行うべきですか?
一般的には四十九日の忌明け法要が終わった後に処分します。宗教や宗派によって異なる場合がありますので、菩提寺や葬儀社にご確認いただくと安心です。
まとめ

あと飾り祭壇は、故人との最後の時間を大切に過ごし、心の整理をつけるための大切な場です。川越の地域性や宗教・宗派によって飾り方や期間が異なるため、不安な点があれば、ぜひ専門家や葬儀社、菩提寺にご相談ください。私たちは川越の皆様の心に寄り添い、少しでもお力になれるようサポートいたします。問い合わせください。

監修者
株式会社ルピナス 金子雄哉
全国の葬儀社を対象にしたコンサルティング及びマーケティング支援を行う、株式会社ルピナスの金子雄哉です。葬儀業界のデジタル化を推進し、より多くの人々が葬儀サービスを理解し、アクセスしやすくするための戦略を日々研究・提案しています。葬儀社の経営者様だけでなく、ご遺族様にとっても最良の葬儀が行えるよう、マーケティングの観点からサポートしております。